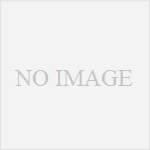クラシック音楽にも「流行」があった!〜時代と共に変わる音楽のスタイル〜
現代のポップスやファッションと同じように、クラシック音楽にも時代ごとの「流行」がありました。
その流行は、作曲家や聴衆の嗜好を大きく左右し、音楽史ではいくつかの「時代」に分けて捉えられています。
今回は、ヴァイオリンでよく演奏される曲の背景を知るために、代表的な三つの時代の特徴を見ていきましょう。
豪華絢爛な「バロック時代」(1600年頃〜1750年頃)
バッハやヘンデルが活躍したこの時代の音楽の特徴は、装飾音が多く、全体として豪華で華麗であることです。
具体的には、対位法という複雑な作曲技法が使われ、複数の旋律が絡み合いながら豊かな響きを生み出します。そのため、当時の聴衆は、複雑な構成と技巧的な演奏を楽しみました。
ヴァイオリンでは、ヴィヴァルディやバッハなどの協奏曲が多く作曲されています。
シンプルで美しい「古典派時代」(1750年頃〜1820年頃)
モーツァルトやベートーヴェンが活躍したのがこの古典派時代です。バロックの複雑さから一転し、シンプルで整然とした形式が好まれるようになりました。
その結果、ソナタ形式や交響曲といった、今日まで続く重要な形式が確立した時代でもあります。
したがって、メロディーは明快で、聴き手に親しみやすい音楽が増えました。調和とバランスを重視した、優雅な美しさが特徴と言えるでしょう。
感情豊かな「ロマン派時代」(1820年頃〜1900年頃)
ショパンやチャイコフスキーなどが活躍したロマン派時代になると、作曲家の「個人的な感情」や内面がより重視されるようになりました。
すなわち、自由な表現と強い感情が音楽に込められ、形式よりも情熱が優先されます。
オーケストラの編成は大きくなり、音色の変化も非常に豊かになりました。さらに、物語や風景を描写する標題音楽も多く誕生しています。
時代ごとの流行を知ることで、クラシック音楽の奥深さが一層わかります。次に演奏を聴くときは、その曲がどの時代の流行の中で生まれたのか、想像しながら楽しんでみてください。